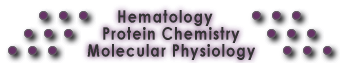News & Topics 【研究室の亀の歩み】
News & Topics 【研究室の亀の歩み】暫く、このコーナーの更新が途絶えてしまいました。それというのも、数々の出来事に忙殺された結果であります。その中でも、文部科学省「魅力ある大学院教育」イニシアティブの拠点公募があり、諸先生方と一緒に相当力を入れてプログラムを組み立て、大学院生命理工学専攻として応募しました。、それが無事に選抜されて「異分野融合型PBL-自立創造的研究者養成」プログラムが採用(リンク)となったことは、私達の今後の教育・研究を通じた人材育成にとって大きな励みになることでした。また、ハリケーン被害の余波で今年度の米国血液学会(ASH)がNew OrleansからAtlantaに開催地が変更され(よくぞ開催地変更が可能になったものです)、慌しくもラボのメンバー5名でASHに参会できたことも嬉しいことでした。最近では、2007年度に新しいビルディングへ移動する話が浮上しており(リンク:東京女子医科大学と早稲田大学との国有地共同取得に伴う生命医療分野における教育研究推進事業に関する概要)、その設計準備などで忙殺されています。
いずれ落ち着きましたら、この欄で空白にしてしまったラボの歩みを追記いたします。
山本雄介が落谷先生と大阪に出向き、第4回 日本再生医療学会での発表を無事に努めました。
今年も研究報告会を開催します。会の後、生物学教室セミナーもあります。興味ある方々のご来聴を歓迎いたします。
入試期間となり、構内は非常に静かです。当研究室では他の研究室と同様、普段と変わらず、毎日学生が実験を続けています。
1月は学生にとっても教員にとっても忙しい時期です。皆、卒業論文、修士論文、博士論文などなどにかかりきりになりますし、文章にしていく過程で、不足していた実験に気付いて、大慌てになります。
その一方で、当生物学教室に導入される質量分析器の搬入を控えた部屋の工事がほぼ終了し、私達の向かいの実験室にMALDI-TOF-MSが搬入されました。機種は島津製作所のAXIMA CFR-plus です。これを使って今年度より、学部3年生を対象に、質量分析法の実験実習を取り入れます。ポリペプチドの限定酵素分解や、Peptide Mass Fingerprintingによる分子同定など、いわゆるポストゲノム時代に不可欠な基本技術として、実際に経験してもらう予定です。大学院に進学後は、ごく日常的に活用してくれることと期待しています。
研究の方ではFACSも使えるようになりましたし、遺伝子実験施設も充実してきました。蛋白質精製用と分析用のクロマトグラフィーに加えて、ここでMALDI-TOF-MSが実験手段に加わりましたから、ようやく大抵のことはon-siteで実施可能となりました。
12月は毎年、日本分子生物学会と米国血液学会(ASH)の開催時期がバッティングします。今年も米国血液学会の方は、加藤、会沢(下記のように筆頭発表)、小坂、野川、日本分子生物学会の方は落谷先生、山本、生田目が出席です。山本と生田目の発表は以下の通りです。生田目は学会発表初デビューです。
生田目奈知,竹下文隆,加藤尚志,落谷孝広.
サイクリンD1 過剰発現によるケラチノサイトでのVEGF の発現上昇(2004.12.10)
山本雄介,寺谷工,村田成範,池田理恵子,木下健司,松原謙一,加藤尚志,落谷孝広.
ES 細胞の肝細胞分化及び成熟化を制御する分子メカニズムの解析. (2004.12.9)
ASHに参加した面々は、San Diegoに約1週間滞在しました。規模の大きい学会ですが会期中には実に様々な交流が実現し、学生達には一生の思い出になったことと思います。
理工学部応用化学科の常田教授が管理されているセルソーター(FACS:BD FACSAria)を今後共同利用させてもらうことになりました。帰国後、学生達とメーカートレーニングを受けました。カエルの細胞は難儀しそうではありますが、ちょっと面白そうな解析結果になりそうです。また、石田が作出した抗血球モノクローナル抗体は良好に使えそうな感触だったので、ホッとしています。
第77回 日本生化学会大会(横浜)のワークショップ:間葉系細胞分化(Mesenchymal cell differentiation)で発表します。この演題はポスター発表も行います。(会沢洋一)
Aizawa Y, Nogawa N, Kosaka N, Maeda Y, Watanabe T, Ochiya T, Kato T.
The development of anemia by the administration of soluble erythropoietin receptor homologue in Xenopus.
昨年度は経済産業省の開発事業として、複数領域の先生方と、MOT (Management of Technology) のカリキュラムをつくりました。今年度、その一部を大学院理工学研究科の共通科目の授業として設置し、初回授業を済ませました。こういう場合だけ、企業勤務経験が多少役に立ちます。(大学は独特の社会をもつため、これ以外にほとんど役に立つことはありません。)
大学院修士9月入学生として、新人1名が加わりました。(村上聡)
米国血液学会(ASH;12月)は採択審査がかなり厳しいので、どきどきしておりましたが、Animal Models Studying Development of Embryonic and Adult Stem Cellsのセッションに演題が採択されました。(会沢洋一)
Aizawa Y, Nogawa N, Kosaka N, Maeda Y, Watanabe T, Miyazaki H, Ochiya T, Kato T.
Expression of erythropoietin receptor-like molecule in xenopus laevis and the development of anemia by the administration of its recombinant soluble form.
46th Annual Meeting of the American Society of Hematology, San Diego, California, 2004
第2回国際幹細胞学会(ISSCR)で、落谷先生との共同研究の成果を小坂展慶が発表します。
無事、ボストンから戻ってこれるかどうか・・・
Kosaka N, Sasaki H, Kodama M, Yamamoto Y, Kato T, Ochiya T.
A role for the fgf-4 gene in the regulation of neural stem cell differentiation.
The 2nd Annual Meeting of Int'l Society for Stem Cell Research, Boston, USA, Jun 10-13, 2004
文部科学省 私大 研究設備等 整備費で設置された、
「生物個体レベルにおける遺伝子機能発現解析研究施設」がいよいよ利用開始となりました。
理工学研究科生命理工学専攻の客員教授として、
国立がんセンター研究所 がん転移研究室 落谷孝広 室長 に就任していただきました。
研究室開設2年目、2人目の学部卒業生が巣立ちます(谷紘江:東京大学 院へ進学)
谷さんは順天堂大学医学部(第二解剖)の石龍徳先生に大変お世話になりました。
研究室開設2年目、2003年度研究発表会を開催します。
学部4年の山本雄介の学会デビューは口演となりました。
周囲はハラハラしていましたが、本人はそんなものどこ吹く風、堂々と済ませました。
ES細胞から肝細胞への分化に関与する核内転写因子の解析
Expression profiles of transcription factors in hepatic commitment of ES cells..
第26回日本分子生物学会年会・神戸国際会議場(2003.12.10)
第76回 日本生化学会大会(横浜)にて、初の当研究室の学会発表です。
野川菜美も小坂展慶も初めての学会発表です。小坂の演題は落谷先生のご指導の賜物です。
Nogawa N, Hiraga N, Aizawa Y, Ikebuchi K, Miyazaki H, Kato T.
Evaluation of alteration in peripheral blood cell counts in adult Xenopus laevis responding to hematopoietic growth factors.
Kosaka N, Sasaki H, Minakuchi Y, Kato T, Terada M, Ochiya T.
Study of FGF-4 gene functions in neural progenitor cells using a small interfering RNA.
研究室初めての合宿を実施しました。BBQ、テニス、ソバ打ち、パラグライダーなど。
長野県 姫木平エコーバレー ホテル アンデルマット
アンデルマットの方々には大変お世話になりました。
大学院博士後期課程の社会人9月入学生として1名の新人が加わりました。(計良陽子)
計良さんは、国立精神・神経センター神経研究所 疾病研究第一部 (西野一三部長)に勤務(CREST)しています。
カリフォルニア(La Jolla)のThe Scripps Research Institute にて、卒業研究の導入として修行した下地美也子が無事に帰還しました。イラク紛争のあおりを受けて、日本との行き来には苦労させてしまいましたが、長い間、ご苦労様。Sanford Shattil教授や江藤浩之先生には大変お世話になりました。
当研究室最初の記念すべき学部卒業生(平賀信幸:都立大院へ進学)が学外へ巣立ちました。
研究室開設1年目、2002年度研究発表会を開催します。どんなことになることやら。